宝塚を好きになってしばらく経つと、「贔屓の卒業」という現実を目の当たりにする瞬間がやってきます。
最初は「まだ私には関係ないかも」「ずっと見ていられる気がする」なんて思ってたとしても、ファン歴を重ねるうちに、いつか多くの人が直面するテーマです。
私自身も、贔屓の卒業を知ったときには「信じられない」「この先どうしたらいいの?」という感覚になりました。私の場合(礼真琴)は、みんな覚悟していましたから「やっぱりそうだよね」って、感じでさほど驚きはなかったですが。
でも、時間とともに少しずつ消化していく過程があって、その中でファンとしての考え方が変わってきたな、という実感もあります。
今回は、初心者の方にも「将来的にこういうことがあるかも」と思ってもらえるように、そしてベテランの方にも「ああわかる」と共鳴してもらえるように、ファンの経験を交えながら、贔屓卒業後の道筋を探るヒントをお伝えしたいと思います。
卒業発表〜千秋楽までの揺れ
- 発表直後の衝撃
一般的には「夢じゃないか?」というような現実感のなさ。SNSや公式発表で「本当なんだ…」と理解する瞬間。私の場合のように、ある程度予想できる場合でも、実際に発表になっても最初は現実感がないですね。 - 情報漁りフェーズ
発表された千秋楽の演目、特別番組、ファンクラブ特典、グッズ発売予定などをチェックする日々が続く。 - 公開される思い出モーメントに心揺さぶられる
スカステ特番、過去作品再放送、OGインタビュー、退団記念DVD…… 情報が次々出てきて、気持ちが振り回される。 - 千秋楽直前/当日の感情
「ありがとうを伝えたい」「最後をちゃんと見届けたい」「もっと早くから追っておけばよかった」など、後悔と感謝が入り混じる。
実際、多くのファンブログではこの期間の心境変化が詳細に綴られています。例えば、ある人は「千秋楽前夜は眠れなかった」「最後の挨拶の声を聞いた瞬間に涙が止まらなかった」と書いていたり。
卒業後にファンがたどるパターン(体験談から見る分類)
贔屓の卒業を経験したファンは、その後それぞれ違う道を歩みます。ブログやSNSでも、共感できる声がたくさんありました。
① 観劇を続ける・復帰型
贔屓がいなくても「宝塚そのものが好き」というタイプ。
新しい作品やほかの組を観ながら楽しみ続ける人が多いです。
ベテランファンに多い傾向で、舞台そのものを愛しているケース。
💬「やっぱり舞台そのものが好きだから、誰が出ていてもワクワクするんです」
② 一時離脱 → 復帰型
卒業直後は辛すぎて劇場に行けなくなるけれど、数年たつと「やっぱり観たい」と戻ってくる人もいます。
💬「3年くらい観られなかったけど、久しぶりに行ったらやっぱり宝塚は宝塚だった」
③ 別の贔屓を探す型
新しいスターや組に自然と目が行き、だんだん気持ちが移っていくパターン。
「この人の芝居が気になる」「歌声が好き」など、ふとしたきっかけで次の贔屓に出会うことも。
💬「次の舞台で偶然見た下級生の歌声に心をつかまれて、気づいたらまた追っていました」
④ 特定組オンリー型
贔屓が所属していた組にだけ愛着を持ち続けるタイプ。
「この組だけは見続けるけど、他組は追わない」という声も多いです。
“組そのもの”を推している感覚に近いですね。
💬「あの組には思い出が詰まっているから、今も変わらず見守っています」
⑤ 完全離脱型
卒業をきっかけに「もう十分」と思い、宝塚から離れる人もいます。
ほかの趣味やジャンルに気持ちが移り、観劇そのものをやめるケース。
💬「あのトップさんが去った時点で、自分の中では区切りがついた感じでした」
⑥ 贔屓のOG活動を追う型
在団中のようには観劇しなくても、退団後の舞台やイベント、テレビ出演などを追いかけるタイプ。
「宝塚ファン」から「OGファン」にシフトしていくイメージです。
💬「今は宝塚よりも、OGとしての活躍を応援するのが楽しみになっています」
📌 こうして見ると、卒業後の歩み方は本当に人それぞれ。
自分がどのタイプに近いか考えるだけでも、少し気持ちが楽になるかもしれません。
心を整えるために使える手段・実践アイデア
卒業後ロスを乗り越えるには、受け止めつつ少しずつ歩みを進める“手段”があると感じます。以下は実例を交えたアイデア集です。
気持ちを言葉にする(吐き出す場を持つ)
- ブログやSNSで心情を綴る
「最後の挨拶を見たとき泣いた」「なんでもっと早く行かなかったんだろう」と書くことで、自分の中のもやもやを整理できる。 - コメントやファン仲間との交流
同じ贔屓を見送った人、似た経験をした人たちの言葉に慰められる。 - 手紙や手書きメモに思いを残す
公式には出せないけれど、自分の中で“ありがとう”を言う儀式として。
実際、あるブログでは「卒業後、千秋楽の夜に思い出を書き留めておいたら少し気持ちが落ち着いた」という投稿がありました。
思い出を形として残す・見返す
- パンフレット・公演プログラム・ブロマイドの整理
かさばるけれど、眺めて過去をしみじみ味わえる。 - DVD・Blu-ray を買う/レンタルする
現役時代の舞台を何度も見直すことで、「あのときこの演技を見たかったな」を叶える。 - スクラップ/フォトアルバムづくり
雑誌切り抜き、写真、パンフ一部をスクラップして、贔屓専用ファイルを作る。
ただし、過度に追いかけすぎると“埋もれる”可能性もあるので、適度なバランス感覚を持つのが重要です。
卒業後も関わる選択肢を知る
- OG舞台・イベントをチェック
退団後も舞台出演やコンサート、朗読劇などに出演することが多い。ファンブログでも「OG出演は貴重な再会の場」と語っている人も多いです。 - スカイステージや過去放送で回顧番組を楽しむ
定期的に過去公演や特集番組が放送されるので、“現役じゃないけど映る贔屓”に会える。 - ファンクラブやOG会などに残る/参加する
ファンクラブを辞め切れない人も多く、「ファンクラブを辞めて良かった」というブログもあれば、逆に残っていることで情報を追いやすくなるという声もあります。 - 次の贔屓をゆるく探す
「この人も素敵だな」と感じた役者を少しずつ追っていく。必ず“トップ”でなくてもいい。
卒業は終わりじゃない:関係性の再構築
ファンとしての関わり方を自由に選ぶ
卒業前と同じように“贔屓を追う”とは限りません。
大事なのは「自分が楽しめる関わり方を見つけること」。
例えば:
- 完全に現場追いかけないけど映像で追う
- 観劇ペースを落とす
- 他ジャンルも交えながら宝塚を“たまに見る趣味”にする
ベテランファンの記事には「トップ退団後、浪費しすぎないように節度を持った楽しみ方を意識している」と書かれているものもあります。
卒業は“区切り”だけど、その先を知ることが深みになる
卒業は、単に「贔屓がタカラヅカを去る」という事実ではありません。
それ以降の言動、活動が、ファンにとって“思い出をどう更新していくか”を問う機会になります。
実際、あるブログでは「退団後の言動で推しの印象がまた変わった」「今まで知らなかった魅力を見つけた」という声も見られます。
だからこそ、卒業後も完全に“忘れる”より、少しずつ“変わっていく姿”を見守るのもまた一つのファンスタイルだと思っています。
締め:卒業を経験しても、宝塚との縁を紡ぎたいあなたへ
贔屓の卒業は、確かに寂しさや迷いを伴う出来事です。
でも、それをただ「失うもの」だけで終わらせるのではなく、自分がどう関わっていくかを選ぶ機会にもなります。
もしこの記事を読んで、「自分はどのパターンか?」「少しずつ見直してみようかな」と思ってもらえたら嬉しいです。
そして、この記事を読んだ初心者の方にも、「ああ、この先こういうこともあるんだな」と思って備えられるような一助になれば嬉しいです。
さて私の場合は、上で書いたパターンなら①番ですね、今のところ。それもかなり薄いですが。周りに花組ファンがいるので花組を見たり、見たい演目を見るということで今までほとんど見なかった月組のガイズを見たり。
もちろん星組のメンバーは下級生の頃から見ているので、カノンやきわみしんの舞台も見に行くでしょう。
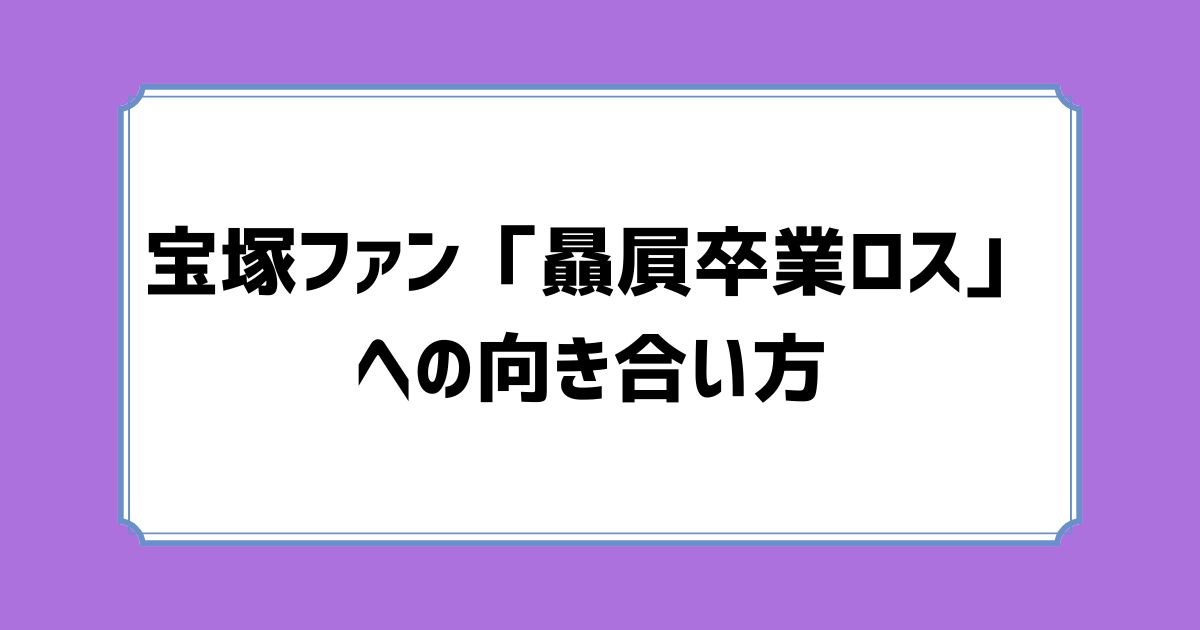
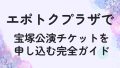
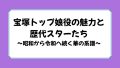
コメント